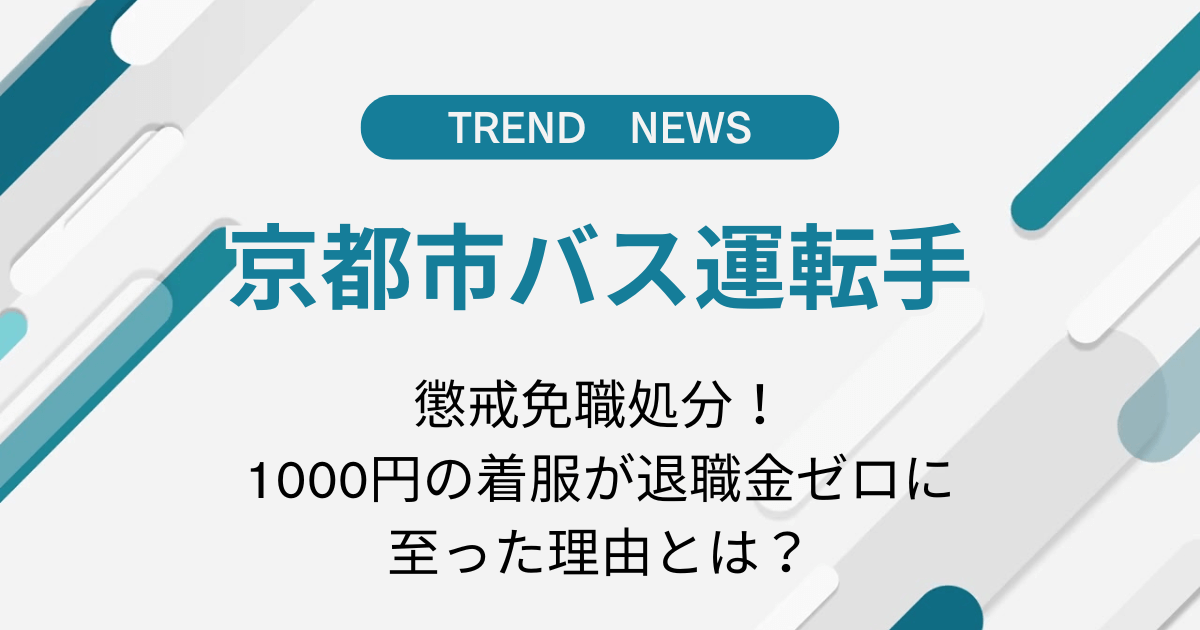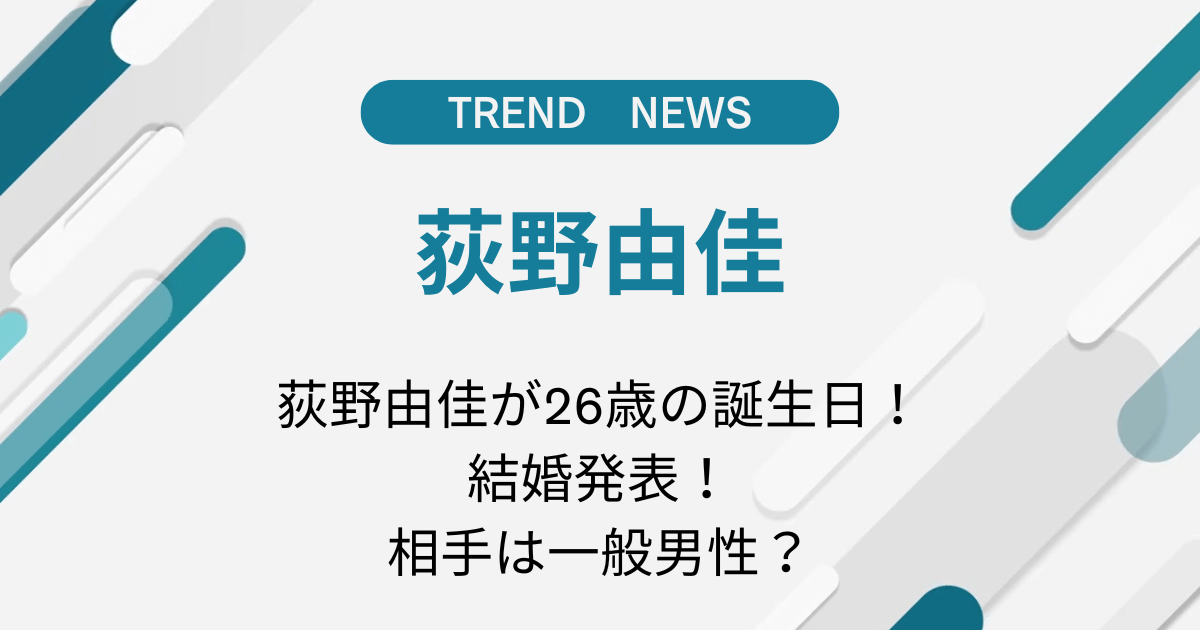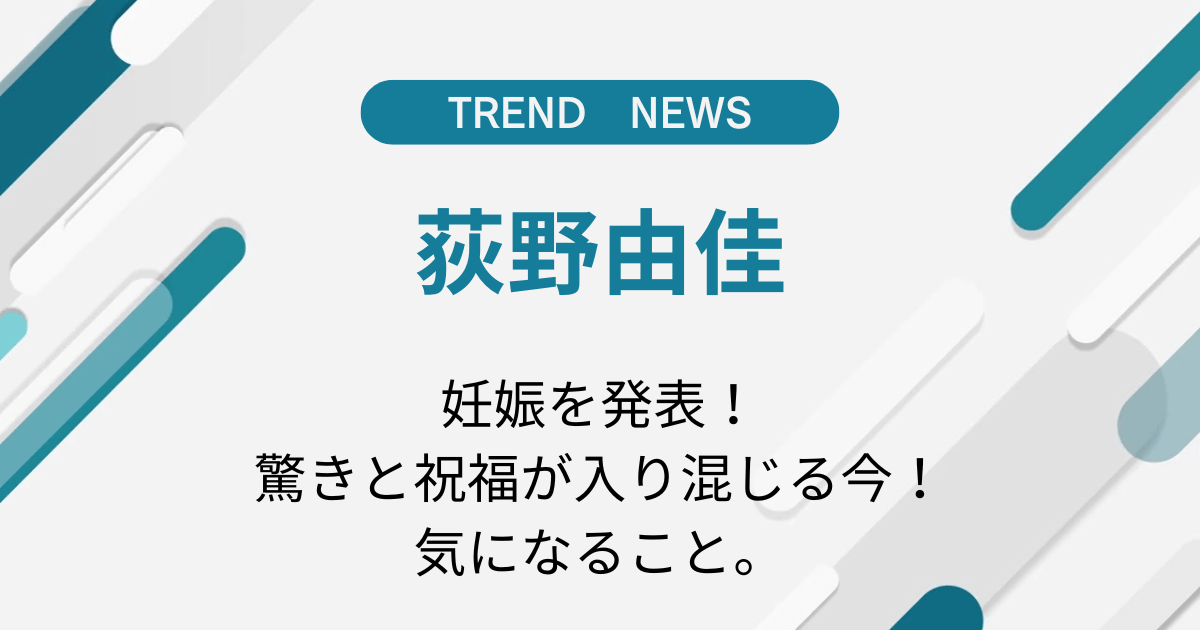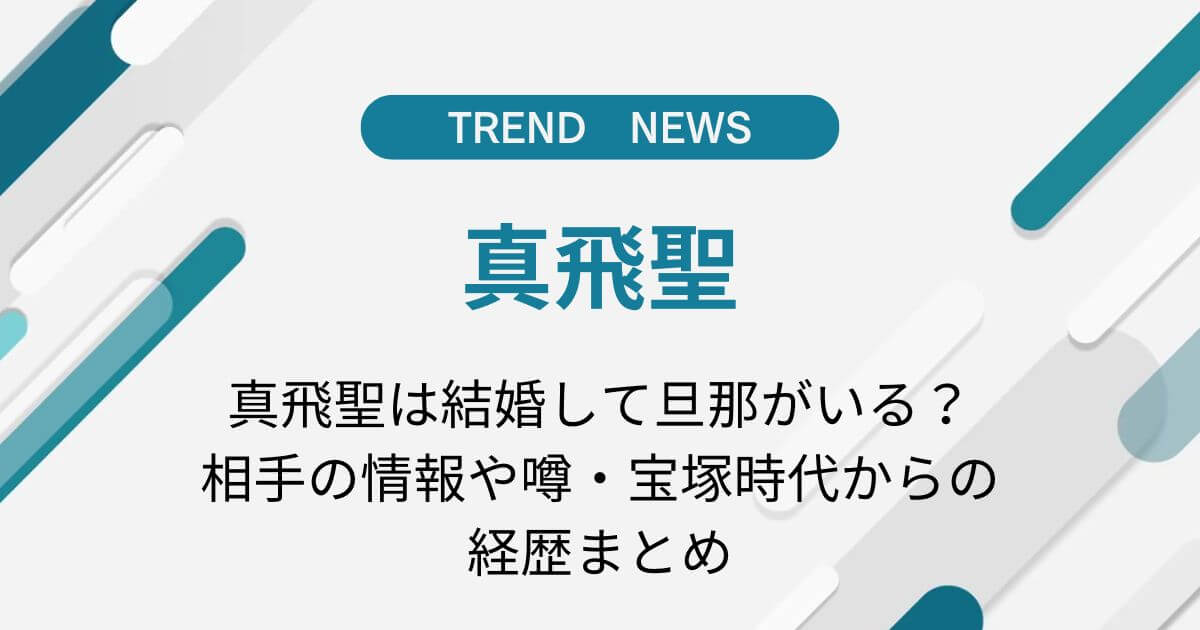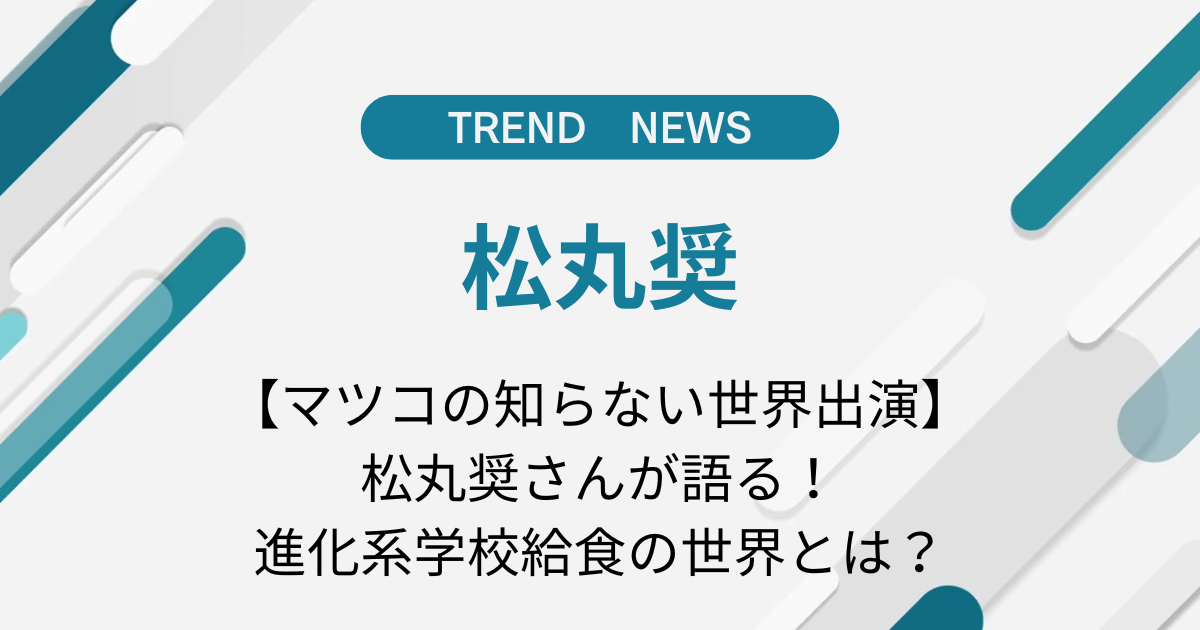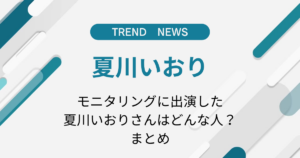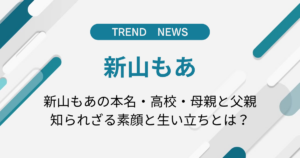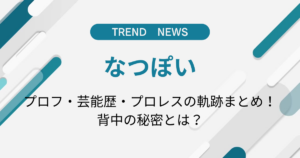バス乗客の運賃1000円を着服したとして懲戒免職となり、約1200万円の退職金も不支給とされた京都市バスの元運転手(58)が、市に処分の取り消しを求めていました。
この訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は4月17日、処分を重すぎるとした2審判決を破棄し、退職金不支給は適法であるとの判決(裁判官5人全員一致)を言い渡し、元運転手の逆転敗訴が確定しました。
今回の判決には、感情だけでは語れない「制度的な背景」と「司法の論理」があるのも事実です。
「たった1000円」では済まされなかった判決の全貌
2025年に起きたこの事件は、金額だけ見れば「1000円の着服」という小さな話です。
最高裁まで争われたこの裁判は、“たった1000円”の問題ではなかったことを、判決にて示しました。
事件の発端は、奈良市交通局の元バス運転手が、5人の乗客から合計1150円の運賃を受け取り、1000円を着服したというもの。
この行為が発覚したことで、彼は懲戒免職となり、本来支払われるはずだった約1200万円の退職金も支給されませんでした。
本人は「金額がごく少額で、処分が重すぎる」として、奈良市を相手取り退職金の支払いを求めて訴訟を起こしましたが、裁判所の判断は一貫して厳しいものでした。
- 一審・二審ともに、退職金不支給は妥当と判断。
- そして今回、最高裁も上告を退け、処分の適法性が確定。
つまり、日本の司法は「金額の大小にかかわらず、公務員としての信用を裏切った行為は重大」と見なし、“信頼に値するかどうか”を処分の基準としたわけです。
ここで気になるのは、



え、1000円位で?



民間なら注意で済みそうだけど…
という感覚。
たしかに、金額としては決して大きくありません。
なぜここまで重い処分になったのか? この判決が意味しているのは、「金額の大小ではなく、信頼を裏切ったかどうか」が処分の判断基準になっているということです。
なぜ退職金がゼロに?裁判所が重視したポイント
1000円の着服で退職金ゼロは、一見すると釣り合っていないように思えます。
しかし、裁判所が見ていたのは金額の多寡ではなく、信用の喪失でした。
今回のポイントはここです👇
判決は金額ではなく「信用」が焦点だった
バス運転手という立場は、乗客の命を預かり、現金を取り扱う職務でもあり、故意に釣り銭を返さなかったというのは、職業的信頼を大きく損なう行為と判断されました。
裁判所が重視したのは以下のポイント:
- 故意の不正だったこと
- 業務中に起きたこと
- 金銭を扱う立場だったこと
- 市民からの信頼が前提の仕事だったこと
つまり、「1000円くらい大したことないでしょ?」という感覚は、“市民の信頼を前提に働く公務員”という立場では通用しないということです。
判決の主文はこちらからご覧ください。
令和6年(行ヒ)第201号 懲戒免職処分取消等請求事件
令和7年4月17日 第一小法廷判決
「退職金は当然もらえるもの」ではない
もうひとつの論点は、「退職金ってそもそもどういうものか?」という点です。
退職金は労働の対価の後払いではありますが、公務員の場合、地方公務員法や条例によって、不正があった場合には減額や不支給にできると明記されています。
今回の判決では、このルールに則って「懲戒免職に相当する重大な非違行為があった以上、退職金を支給しないのは適法」とされたわけです。
つまり、今回の判決はこういうことを言っています👇
「金額の大小は関係ない。“信頼に値する行動かどうか”が全てだ」
これが、感情ではなく制度として下された判断のロジックです。
「退職金は当然もらえる」は勘違い?公務員のルールとは
「何十年も働いてきたんだから、退職金はもらって当然」
そう思う方がいるかもしれませんが、公務員の退職金にはもらえない条件が明確に定められています。
公務員の退職金には“支給制限のルール”がある
公務員の退職金は、各自治体の条例や規則に基づいて支給されます。
そしてその中には、次のような条文が存在します。
「懲戒免職処分を受けた者に対しては、退職手当の全部または一部を支給しないことができる。」
これはつまり、不正行為や重大な違反があった場合には、退職金が“当然には支払われない”という制度設計になっているということ。
今回の京都市のケースも、市の条例に基づいて「不支給」とされたわけです。
処分の“重さ”が判断基準になる
退職金が出るかどうかは「どれだけ悪いことをしたか?」ではなく、「どの処分を受けたか?」で決まります。
- 戒告や訓告などの軽い処分
- →原則、退職金支給される
- 停職や免職などの重い処分
- → 条例により「全額不支給」「一部減額」の対象に
特に懲戒免職は最も重い処分であり、信頼関係の完全な破綻を意味するため、退職金の全額不支給が当然とされる過去の判例が多く存在します。
「一回のミス」で免職もあり得る
一度のミスでも、故意であれば「信用失墜」として重い処分が下されやすい土壌があるのです。
要するに、公務員にとって退職金は
「真面目にやり遂げたことへのご褒美」ではなく、
最後まで信頼されていたかの結果として与えられるもの。
他にもある!似たような退職金不支給の事例を紹介
では、他にもこんな事例はあるのか?
実際に退職金が不支給・減額された他の事例を紹介していきます。
事例①:勤務中のパチンコ通い → 退職金不支給
場所:神奈川県の市役所職員
業務時間中に頻繁に職場を離れてパチンコをしていたことが発覚。
→ 懲戒免職処分+退職金は全額不支給に。
このケースも、「税金で給料をもらっている立場」としての信頼を著しく損なったと判断されました。
事例②:交通違反の隠蔽 → 退職金一部減額
場所:福岡県の警察官
飲酒運転をした上司の違反記録をもみ消した部下が懲戒処分。
→ 懲戒免職には至らなかったものの、退職金は規定に基づき一部減額された。
これは“直接の不正”ではなくても、組織ぐるみの隠蔽に加担したことが重く見られた例です。
事例③:飲酒運転 → 懲戒免職&退職金全額不支給
場所:北海道の消防士
飲酒運転で人身事故を起こし、懲戒免職に。
→ 市民の命を守る職責にある者として、信頼回復は不可能とされ、退職金はゼロに。
つまり今回の判決は、過去の判断と比べても決して突飛なものではなかったということです。
まとめ:厳しすぎる?妥当?
たった1000円の着服で、1200万円の退職金がゼロ。
この判決には「厳しすぎる」、「いや、当然だ」様々な意見がネット上に書かれています。
今回のニュースが投げかけているのは、「行為の大小ではなく、信頼を裏切ったかどうか」という根本的な問いです。
この記事で見てきたように、
- 裁判所は金額よりも信用の有無を重視した
- 公務員には、市民の信頼を守る責任とルールがある
- 信頼重視の風潮は今後さらに強くなる可能性がある
今回の記事は以上となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。